今回は・・・
ダラダラ食いについてお話していきます!
だらだら食いをするとどうなる?
普段、お口の中は中性に保たれています。
数値で表すと、pH(ペーハー)7.0程度です。pHとは、酸性やアルカリ性の度合いを示す単位です。
食事をすると、歯垢(プラーク)の中の細菌(ミュータンス菌など)が、食べ物や飲み物に含まれる糖をエサにして、酸を作ります。
すると・・・お口の中が一気に酸性に傾き、pH5.7程度まで下がると、酸が歯のエナメル質を溶かしはじめます。
これを「脱灰(だっかい)」と言い、虫歯の原因になります。
ただ、ずっと「脱灰」が続くわけではありません。
唾液には酸性を中性に戻す働きがあるため、食後30分〜1時間弱かけて、お口の中は中性に戻ります。
これを「再石灰化(さいせっかいか)」と言い、脱灰によって失われたカルシウムやリン酸を補ってくれます。
※みなさんは、「ステファンカーブ」をご存知でしょうか。
ステファンカーブとは、人のお口の中のpHの上下をグラフに表したものです。
ちなみにpHとは、酸性とアルカリ性の値を表したものです。
お口の中では、このpHの値の変化によって「脱灰」と「再石灰化」が繰り返されているのです。
お口の中に糖分(特に砂糖)を含む食べ物が入ると、数分で口の中が酸性になり、
歯が溶け出すpH(臨界pH5.5)にまで低下すると、
エナメル質から歯の成分であるカルシウムやリンが溶け出します。
この過程を「脱灰」といいます。
その後、時間が経つにつれて、だ液の働きによってpHは高くなっていき、
溶け出した歯の成分は元に戻ります。これを「再石灰化」といいます。
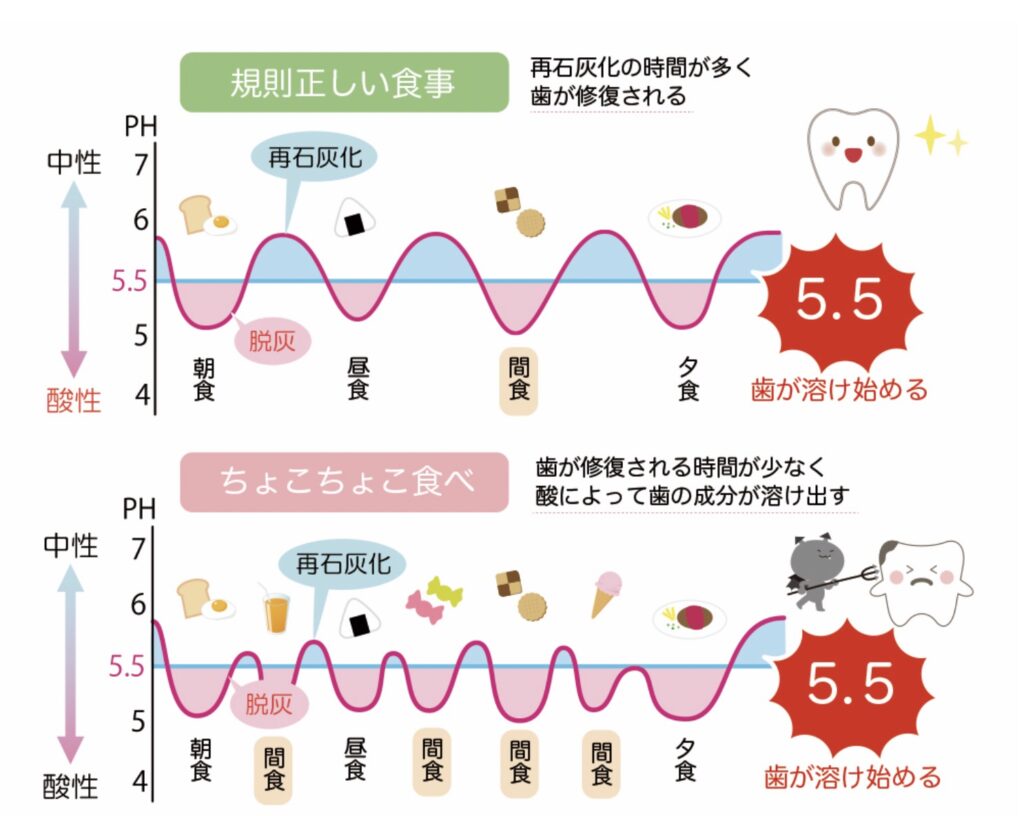
【 食生活の改善が、虫歯予防になる!! 】
虫歯になるリスクを減らすには、次の3点が大切です。
1 “ダラダラ食い”をしない
2 唾液の分泌を促す
3 食後にしっかり歯磨きをする
1 “ダラダラ食い”をしない
⇢ついつい、ダラダラと食べ続けてしまう方は、お口の健康を意識して、時間を決めて食べるようにしましょう。
2 唾液の分泌を促す
⇢唾液はお口の中を中性に戻してくれる、大切なものです。
口呼吸をする癖がある、あるいは加齢などによっても唾液の分泌量は減少します。また、就寝中も唾液の量は減ってしまいます。
唾液の分泌量を増やす方法として、「ガムやタブレットを食べる」ことがおすすめです。
特に、キシリトール配合のガムを噛むと、虫歯の発症がおさえられることが分かっています。
キシリトールは細菌(ミュータンス菌)に分解されず、酸が作られません。また、カルシウムと結合するため、歯の再石灰化が促されるのです。
≪ 虫歯予防のためには、キシリトールが50%以上含まれているガムなどを、毎食後に5g 〜10g摂取するのが良いとされています。 ≫
3 食後にしっかり歯磨きをする
⇢歯磨きをすると、歯の表面に付着したプラークを落とすことができます。
歯と歯のすき間など、歯ブラシが届かない箇所は、歯間ブラシやフロスを使って歯垢を取り除きましょう。
どうしてもセルフケアで落としきれない汚れは、歯科医院の定期クリーニングできれいにすることをおすすめします。
お困りごと、気になることがございましたら
お気軽にご相談ください。

